
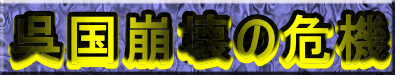
祖国の危機を、”異国の地”で知る羽目となった重臣が居た。然も、唯独り、〔敵国の首都〕に於いて、 「孫策死す!」 の悲報を聞いたのであった。
『呉ニ2張在リ!』 と謳われた、2人の重臣のうち・・・・強面の【張昭】が1人、国内で新君主の尻を叩いて孤軍奮迅の叱咤激励を浴びせて居た時・・・・”2張”のもう1人・物静かな【張紘】も亦、敵地に在って、若き新君主の為に孤軍奮闘して居たのである。
 【張紘子綱】は、昨年の暮れに、孫策の密名を帯びて、《曹魏》へと赴いていた。表向きの公式任務は、孫策が〔呉侯・討逆将軍〕に任官された事に対する、「献帝」への”御礼言上”であった。無論、任地は『許都』であり、その最大の任務は・・・・
【張紘子綱】は、昨年の暮れに、孫策の密名を帯びて、《曹魏》へと赴いていた。表向きの公式任務は、孫策が〔呉侯・討逆将軍〕に任官された事に対する、「献帝」への”御礼言上”であった。無論、任地は『許都』であり、その最大の任務は・・・・〔献帝の呉国への動座!〕であった。
迫り来る《官渡の大決戦》を目前にする今、いざ決戦が始まった暁には、孫策率いる5万の呉軍が、曹操の背後から許都を襲撃。献帝を呉国にお移し奉る・・・・と云う大戦略・筋書きの下準備の為に、朝廷との間で事前承諾を取り付けて措く事ーー其れが張紘の使命であったのだった。
それに対する曹操・・・・先刻、その企図は察知済み。逆に、その動向を探ろうとしてか、張紘には一切の行動制限を設けず、宮廷への出入りも御構い無しで、オールフリーの自由行動を許していた。 その為、張紘としては、帝の取り巻き・廷臣達に、孫策からの密名を伝え、その同意を深める機会も増えていた・・・・。
だが、曹操はもっと上手だった。廷臣に拠る〔曹操暗殺計画〕が発覚した!・・・・として、この正月に、献帝周辺の廷臣グループを根こそぎ大粛清してしまったのだった!!(※ 詳細は第44節にて述べる。)
ーー是れは、張紘一代の不覚であった。この曹操の荒療治に因り、〔献帝動座〕の密名の実施は、俄然、不具合を招来してしまった。そして其の儘、機を窺う裡に日々は過ぎ、遂にーー『孫策死す!』の悲報が届いたのであった・・・・。
この、事態の急展開に拠り、おのずと張紘の立場と役割は激変した。梟雄・曹操との新たな駆け引き、祖国動乱を控えた上での外交交渉が、愁眉の急となった。呉国を代表する外務大臣としての、張紘の力量が問われる事となったのである!
当然、先ず考えられるのは・・・・曹操が此の事態を絶好のチャンスと捉え、呉国討滅・呉国併呑を念頭に描く事である。官渡戦が動き出さんとしている今、直ちに動ける状態では無いが、断じて其の機運を阻止し、其の策動の不可なるを、曹操本人に知らしめなくてはならない。
「孫策殿には、此のたび誠に御気の毒で在られたな。心から御悔み申し上げる・・・・。」
そして此処からが、曹操の真意であった。
「処で、どうじゃな。此の際、張紘殿とも親しくなれたし、ひとつ儂に仕えては呉れまいかのう〜。貴殿の大才は、この曹操、とくと拝見させて戴いた。厚く遇するのは当然として、呉の地も当主を失い、心許無い限りじゃしな。それに跡を継ぐ孫権とやらは、未だ18歳の子供だと謂うではないか?」
曹操は早速、探りを入れて来た。
孤立無援、敵地に唯一人の張紘であった。然も今や、自分を招いて呉れ、臣従を誓った”直接の主君”は死んで居無い。曹操が誘う如く、確かに今の時点では、張紘が誰を新しい主君と選ぼうとも、それは非難に値する事では無かったし、社会的にも許される事ではあった。
だが一方、曹操も亦、苦境に在った。「官渡の戦場」では、【袁紹の大軍】に攻め寄せられていた。今、呉に背後を脅かされるのは、何としてでも避けねばならぬ逼迫状況下に在る。
「これは又、曹操殿とも在ろう御方の言葉とも思えませぬな!」
喪服姿の張紘が、グイと細い体を伸ばした。
「もし今、喪服を着けた私が、曹操殿の御誘いを受けましたなら、私めは勿論、曹操殿も亦、世の人々から礼節を弁えぬ輩として、罵りを浴びること必定と存ずる。礼教を尊ぶ人士からの非難は轟々と巻き起こるで御座いましょう。
その上、亡き孫策殿はつい先頃、朝廷より正式に呉侯の官位を賜わり、江東に於ける正統性を認められたばかりに御座います。
それを喪中と云う事で否定し、覆すなどの処遇いたさば、曹操殿の名望は一挙に地に堕ち、今後の覇業にも大きな支障と成りましょう。」
張紘は曹操を眼の前に、一歩も退かぬ堂々たる態度で、自論を開述する。
「まして他人の死去を好い事に、仮初めにも、その喪中を襲うなど、凡そ人たる者の道に外れた愚行と申さざるを得ませぬ。
此処は寧ろ、喪中の者達への哀れみを施し、天下に礼節の何たるかを御示し為されるのが得策。そもそも初代・孫堅、2代・孫策とも、魏国との好みを通じて参りました。又、漢室への忠心も明らかで、臣としての身分を重んじて来て居ります。その孫呉政権に対し今、弱味に付け込み、死者に鞭打つ如き言動を採るべきでは御座いますまい。」
実際の処、孫策が急死した事に一番ホッとしたのは、曹操の筈である。表面上は友好関係を保ちながらも、決戦中に何時、背後を突かれるかとヒヤヒヤして居たのだ。『小覇王・孫策』には、それだけの気概と覇気が有った。それ故、張紘も人質同然に足止めされ、互いに様子を窺い合って来たのである。
だが、其の危機は去った。折角出現した此の好ましい状況を、下手に突いて蒸し返すなど、愚の骨頂である。
「天下に覇を成さんとされる方なら、今は仁者として、孫氏3代目にも慈愛を掛けられ、慰撫される事こそ、王者の振舞いと申せましょう。
これ迄、孫堅には「破虜将軍」、孫策には「討逆将軍」を戴いて参りま
した。 今後とも両国の友好を固める為に、孫権にも其れにちなんだ将軍号をお与え下さりませ。 もし、この事叶いますれば、この張紘、命を賭してでも漢室をお守りし、曹操殿との友誼、必ずや貫き通させて見せまする。」
外交交渉には往々にして、面子・立場と云うものが、大きな意味を持つ場面が在る。ーー曹操側からは言いたくとも、先には切り出せぬ、大国の面子と云うものが在った。張紘は、ソコの処を充分に呑み込んで居たのである。・・・・曹操が言いたい腹の内を、此方から誘い出して合意し易くする・・・・それも外交手腕と謂うものである。国家の威信を擽(くすぐ)ると云う訳だ。
「−−さて、この張紘子綱の言、
曹孟徳殿には如何が思し召されるや・・・・!?」
この張紘の舌鋒は、今置かれて居る両者の情勢を踏まえて、互いが折り合いの着く線へと歩み寄る、巧みな”誘い水”であったと言える。
《−−流石、張紘。袁術弾劾状も書き手だけの事はあるな。
なかなか遣りおるわい・・・・。》
片や、百戦錬磨の曹操である。全て呑み込んだ上での返答となる。
「あい分かった。そなたの申す通りであろう。上表して、孫権殿には「討虜将軍」・「会稽太守」の任に就いて貰う事に致そう。今後とも両国が友好を保つなら、朝廷も其れを喜ばれよう。・・・・それにしても、呉には良き臣が居る事よの!是れで張紘殿も、やっと国に帰れますな。もう足止めは致さぬ。直ちに帰国され、旧主の墓に参られるが宜しかろう。」
【張紘】は独り、敵地に於いて、主君の死と云う突然の危機に見舞われながら、冷静に自他の状況を見据え、曹操との直接交渉に当っては、一転、情熱を以って自説を展開。苦しい状況の中、却って新君主に将軍号を齎し、魏との当面の和平を携えて、祖国・呉に帰還したのである。張紘の、外交官としての真骨頂、面目躍如たる一代の名場面と成った・・・・。

ーーさて、こうして呉の2張が、国の内外に於いて、頻りに盛り立てて呉れている、当の新君主・【孫権】であるが・・・・
その威光の程は、甚だ芳しく無い。
各地に噴出した叛乱の火の手は、鎮静化する処か、寧ろ益々猖獗を
極めるばかりーー。更に情け無い事には・・・本来なれば、兄・孫策の葬儀は〔国葬〕として、呉国全版図の津々浦々にまで布告し、郡県単位の全ての家臣団と、その属する将兵を一同に会して、新君主就任の一大セレモニーを主宰する処であるのだが・・・殆んどの郡県は、叛乱に備えて身動き出来ず、その集合状況は予定の5分の1にも満たなかった。
ーーそんな中、不穏な噂が巷に流れ出した・・・・。
「叛乱軍が1つに纏まって、呉郡に攻め入って来るそうじゃ!」
「いや、西と南の2手に分かれて攻め込んで来るらしいぞ!」
「荊州の黄祖も、長江を下ってリベンジに出て来るそうじゃ!」
「孫権殿で、大丈夫だろうか?」
「未だ、何の実績も無いしなあ〜・・・・。」
「第一、18歳では貫禄不足じゃわい。家臣の方が皆、頼もしい位じゃ
ものなあ〜!」
ーーと、すれば・・・・と、思わず民衆が、互いに顔を見合わせて頷き
合い、ハタと膝を打つ人物が浮び上がって来る。
「周瑜様じゃ!!」
「そうだ、我が呉国には周公瑾様が居られるではないか!」
「ウム、この緊急の際じゃ。いっそ周瑜様が新しい君主と成られて、
我が国を導いて下される方が安心じゃ!!」
「ほんに、周瑜様なら、誰も文句を云う者は居らんぞ!」
ーー今や【周瑜公瑾】の実力は、呉国に於いてナンバーワンである。他者の追随を許さぬ圧倒的格差であり、ナンバーツウは無いに等しい。在るとすれば、それは亡き孫策以外には無い。
孫策政権発足以来、地元揚州の在来勢力は、地元名族たる周瑜の元に結集していた。成り上がり者の孫氏には反発しても、地元名士の周瑜には従う・・・・と云う者が数多く居るのである。
又、重臣・文官の殆んども、周瑜が招聘し、その人柄・人物に応じた者達で占められている。 更に、度重なる戦いの中で、君主と同等の事実上の総司令官として、全作戦を勝利に導いて来た。 その実績と人柄とで、宿将はじめ武人集団を心服させ、ガッチリ纏め上げ、今や軍事面での全権も掌握している。
はっきり言って、その影響力は、孫権を遙かに凌いでいる。その事は周瑜自身、しかと判っている。
『本日より、余が呉の王である!』 と、ひと言告げれば、其れは実現する。周瑜なくしては、呉の国は成り立たないのだ。今、呉国が崩壊しないのも、ひとえに周瑜の存在が有るからこそであった。
又この後も、「呉国の歴史は周瑜の歴史であった」と謂える程の、巨大な存在で在り続ける・・・・。
「周瑜様が帰って来られるそうじゃ!」
「いよいよ、やって来られるか!」
「3万の精兵も一緒らしい。」
「いや、儂は5万と聞いたぞ。」
「10万との噂も有るそうだ。」
「周瑜様なら、その位の力はお持ちだろうな。」
「いずれにしても、頼もしい限りじゃわい!」
「有り難い事じゃのう〜・・・・。」
「さて、周瑜様、どうされるか?」
「うん、どう為されるかなあ〜!?」
ーー周瑜の君主就任待望論である。
そして、呉国民注視の中・・・・ついに、その【周瑜公瑾】が、大艦隊を率いて、長江から上陸して来たのである!
 白馬に赤いマントの貴公子・・・・社会的名声、実績、才能、人柄、実力、風貌・・・・全てに於いて若い孫権を凌ぎ、国民の人望も遙かに厚い。
白馬に赤いマントの貴公子・・・・社会的名声、実績、才能、人柄、実力、風貌・・・・全てに於いて若い孫権を凌ぎ、国民の人望も遙かに厚い。
だが・・・・盟友との信義を貫き、権力欲にすら執着を見せず、清々しい道を選ぶ処にこそ、周瑜公瑾の人としての魅力がある。それ故にこそ人々は一層彼を慕い、信じ、尊敬したのである・・・・。
その最たる一人が、誰あろう、新君主の【孫権】であった。
「−−嗚呼、公瑾どの〜〜!!」
その日、わざわざ城を出て、郊外に出迎えた孫権は、赤いマントの周瑜の姿を見つけるや、人目も憚らず、一直線に駆け寄った。そしてワッとばかりに、周瑜の其の分厚い胸の中に飛び込むんでいったのである。
「周瑜どの!周瑜どの〜!! よくぞ帰って来て下された!よくぞ、よくぞ・・・・。兄上が、兄上が亡くなられてしまったア〜〜!!」
兄を失った悲しみと、心許無さと 不安と重責と・・・・そして今、やっと
最大の後ろ楯に巡り会えた安堵と喜びとが入り混じり、感極まった激情の中に、言葉を詰まらせ、涙をほと走らせたのであった。
「仲謀殿、さぞや御辛かったであろうな・・・・。然し、この公瑾が来たからには、もはや心配は御無用!安心召されよ!」
「うん、私も公瑾殿を真の兄と思い、追いていく。この私を兄同様、宜しく導いて下され・・・・!」
涙に濡れた若者の顔が、周瑜の優しい言葉によって、ようやく少し明らんだ。眼が碧かった。
「・・・・衆人の眼が御座る。宜しいか!是れから私は、孫権様を新たな主君と仰ぐ臣下である事を、文武百官の前で御示し致します。仲謀殿も、此の場は其の様に振舞われよ!孫権仲謀こそ、呉の新しい君主に相応しい御方である事を、この公瑾が知らしめましょう程に!!」
言うと周瑜は、孫権を其の腕の中から離し、己の眼の前に立たせた。ーーそして其の前に、みずから片膝を屈し・・・・恭しく頭を垂れて見せたのである。
〔此の一瞬〕こそが、呉の新君主の誕生であった!
「この周瑜公瑾、全身全霊を以って、新しき御君主。孫権仲謀様に
御仕え申し上げる事を、ここに誓い奉ります。」
言って立つと、サッと腰の軍剣を引き放ち、天空に翳した。そして大音声で叫んだ。
「破虜将軍・孫堅どの、討逆将軍・孫策どのも御照覧あれ!!」
それに呼応して孫権も腰の宝剣を抜くと、宙空で周瑜の剣と交差させる。陽光が2本の剣に宿り、キラリと光った。
 2人は互いの剣を3合すると、最後に、互いの瞳の真ん中を凝視め合った儘、鍔をガチリと鳴らした。
2人は互いの剣を3合すると、最後に、互いの瞳の真ん中を凝視め合った儘、鍔をガチリと鳴らした。「−−・・・・。」
その光景を、固唾を飲んで見守って居た諸将・群臣・兵達の間から、期せずして鯨波が湧き上がった。 是れを観ていた万余の群集が、
それに和した。
剣を収めた孫権と周瑜の2人が、歓呼の中を連れ立って歩き出した。
ーーかくて此処に、新しき呉国の第一歩が、実質的に踏み出される事と成ったのである・・・・。
城に着くなり、周瑜は孫権に勧告して、遠征に出ている全ての軍を、即刻、「呉城」に帰還させる命令を発令させた。
全軍の指揮統帥権を、改めて確認させる為に、〔孫権の名において〕全ての指揮官を任命し直させる事としたのである。新体制と成った事を、先ず形式から徹底し、再認識させようと云う訳である。此処ら辺の「軍人気質」・「武人心」の機微については、文官の張昭には為し得ぬアドバイスであった。ーー軍部、特に実戦部隊の将官の中には、若い孫権を軽く見下す風潮が観られる。だが、後に周瑜がデンと控えて居る事を見せ付けて措けば、その傾向も徐々に修正されるであろう。口で言うより、彼等の眼の前で、総司令官の周瑜が、〔臣下の礼〕を示す事により、効果は数倍にも増すであろう。
ーー周瑜公瑾の気苦労は、未だ未だ当分、続きそうである・・・・。

《−−不味いな・・・・!孤立して居る・・・・。》
周瑜の眼には、其れがハッキリと観て取れた。
今、此処に列席している重臣会議のメンバーは全て、孫堅・孫策の代から重きを成して来た古強者達ばかりである。 若い孫権は君主とは謂え、どこかに遠慮が見受けられる。
ーー若君は其処に黙って控えて居てくだされば、それで充分!
全ては我等に御任せあれ・・・・!!
会議は重臣達が切り盛りし、孫権そっち退けで進んでいく。
・・・・今は未だ当人が、みずから聞き役に徹し、王道を学び取ろうとする姿勢を保って居るから良い。或る意味では、じっくり家臣団の意見を聴けるタイプの〔名君〕に成るかも知れぬ。−−だが今の様子では、どうもそうでは無い。言いたい事も言えぬ雰囲気が在る。重臣達への気兼ね・遠慮が先行している。同時に、彼自身の自信の無さと、未実績から来る不安とが、孫権を〔背景〕へと引き退かせている。
だとすれば、いずれ其のうち、 其のイニシアチブの取れぬ状況に、不満を感ずる日も来よう。その結果、重臣達との無用な軋轢や動揺を生まぬとも限らない・・・・。
《やはり、気心の知れる、同世代の側近が欲しかろう・・・・。》
初代、2代目を知らず、孫権の為だけに仕える、新たな側近を迎えてやらねばなるまい。ちょうど孫策と自分の如き、初めからピッタリ息の合った側近が必要であろう。 何でも気兼ね無く、ズケズケと言い合うには、〔新しい出会い〕が要る。この儘では君主の影が薄く、孫権の孤立感が深まってゆこう。
《ーーおムコ探しをしてやるか・・・・。》
譬えの可笑しさに、みずから苦笑しつつも、周瑜は真剣になった。
だが、誰でも良いと云う訳にはゆかない。国の命運を左右し兼ねない、重い位置に収まるべき人材でなくてはならない。
−−そこで浮上して来たのは・・・・あの、
異形の星の【魯粛】であった!

ここ1両年、交友して来た印象では、彼はリアルな現実主義者だ。
徹底した客観眼を所有している。そして何より、呉の独立を説き、覇気にも満ちている。彼なら、やや退き気味の孫権と好いコンビに成り得る進むべき道を誤る事無く、新君主に語れるであろう。歳も未だ20代と若く、孫権とのウマも合いそうだ。
《共に、新しいスタートを切らせよう・・・・。》
ここの処、戦さに明け暮れて遠方に居た為、正式な出仕要請を促す機会を逸して来ていた。だが今や、攻勢より守勢の時だ。ちょうど今、周瑜自身も、暫くは此の地(呉郡)に居て、新政権の基盤固めをしようとしていた。直ぐにでも会いに行ける。
思い立つと、周瑜は直ぐに行動に移った。魯粛の住まいを「曲阿」に
訪ねた。が、魯粛は不在であった。彼の母親だけが留守を囲って居た。実母の話によれば、祖母の葬儀の為、故郷の「東城」に出向いていると言う。そこで周瑜は母親に事情を話し、その賛意を取り付けると、同道して「呉」に来て貰う事にしたのであった。此処にも亦、『母親の存在』が、深い関わりを持つ、江東の地の特異性が観られる。
ーーさて、その【魯粛】・・・・周瑜との親交を深めるうち、すっかり周瑜の人物に惚れ込み、彼を慕って、400名近い技能者集団を率いて、
この「曲阿」の地に移住して居たのであった。広大な田地田畑を全て処分し、いつ周瑜からの声が掛かっても好い様に、スタンバって居たのだ。・・・・が、その後、周瑜は各地を転戦連勝する状況となり、出仕の話も無い儘、祖母の葬儀と相成っていたのだった。この祖母が巨万の財を築き、ドラ息子なんらぬ”ドラ孫”の魯粛が、其れを投じて政事参加への道を開いたのである。 だから魯粛としては、深く喪に服さずには居られ無い、有り難〜いバア様であったのだ。
その故郷の「東城」に戻り、喪に服して居る折、旧友の【劉子揚】から手紙が来た。
『天下の豪傑並び立つ今日、貴下の才能こそ、時勢の要求に叶った
ものである。何時まで東城に滞在して居る御心算なのであろうや?
近頃、「鄭宝」と云う人物が、巣湖に在って万余の軍勢を擁し、盧江一帯の人材を続々と召し抱えております。我等一党も馳せ参ずる所存です。時を失してはなりませんぞ。早急に曲阿にお戻りあって、母上をお迎えの上、直ちに行動に移るべきですぞ。速やかに御決断あれ!』
魯粛を買うのは、周瑜だけでは無かったのである。魯粛は迷った。
周瑜に肩入れしたい。だが、待てども遂に、周瑜からの声は掛からなかった。孫策も急死し、己の出番は無いかも知れない。半ば諦めかけて居た時でもあったので、彼は旧友に同意の返事を送った。 葬儀が一段落したら曲阿に戻り、改めて巣湖の鄭宝の元へ出仕しようと決めたのであった。
《−−やはり、”名士”で無い者には、大口大手からは、
御呼びは掛からぬのか・・・・。》
半ば落胆のていで、曲阿に戻る魯粛・・・・。処が、曲阿に着いてみると母親は既に、周瑜に伴われて「呉」の地に移った後であった。
《−−これは・・・・!!》
魯粛は吉兆を感得し、すぐ様、母親の後を追った。

【第127節】 刮目すべき奴等(目立たがりの赤備え)→へ