

【諸葛亮孔明】と云う人間の業績を語る時ーー
彼が劉備に出仕した207年春~翌208年の9月迄の
1年半の期間・・・・・これまで誰一人として問題視せず、着目も
して来なかったこの期間は・・・・
実は、非常に重大な《謎》を秘めているのである。
その直前に為されて、あれほど世に喧伝されている
「三顧の礼」・「隆中対」・「天下三分の計」に引き続く重大な実行準備期間である筈にも係わらず、その後の一年半の期間、諸葛亮の行動は、史書において殆んど記されていないのである。謂わば、史書に於ける”真空地帯”、諸葛亮や劉備ファミリーの動きや思考の”欠落期間”なのである。
では何故、この空白期間が重大なのか?
--ズバリ、史実的結果論から言って・・・・ この期間に於ける
『諸葛亮の無為無策ぶりが、露呈されて来てしまう』からに外ならないのである!!
・・・・こんな重大な事実であるにも関わらず、かつて誰もこの点を指摘する事が無かったのは・・・・其れに触れる事自体が〔歴史家のタブー〕とされ、一種の〔アンタッチャブルな聖域〕として見逃されて来たからに外ならない。すなわち、諸葛亮孔明を支持する《圧倒的な庶民感情が発する無言のパワー》に迎合せざるを得無い、社会背景への遠慮・配慮があった為と思われる。
そして同時に又、諸葛亮を識れば識るほど、彼に惚れ込んだ歴史家自身が、諸葛亮の「其の後の事蹟」を汚すまいとする暗黙の配慮、ないしは、好意的無関心、尊崇的黙殺などの ”心理的先入観”を抱いて来た事に由来する為であろう。
だが然し、そうした好意や配慮は、彼・諸葛亮に対する贔屓の引き倒しであり、却って真実の諸葛亮像を冒涜する結果を招くに違い無いと、筆者は思念するのである。
・・・・この1年半後の、208年(建安13年)9月・・・・
劉備の軍師と成って程無い【諸葛亮孔明】は、其の瞬間、
愕然として蒼ざめ、しばし茫然自失の呈で、
言葉も無く立ち尽くす羽目に陥ったのである!!
・・・・一体、何が起こったと言うのか??
ーーすなわち・・・・突如、彼の眼の前に・・・・
 百万の曹操軍が、襲い掛かって来たのである!!
百万の曹操軍が、襲い掛かって来たのである!!
まさに”青天の霹靂”であった!!
諸葛亮孔明を軍師に戴いた劉備ファミリーは、
全くの不意打ちを喰らったのである・・・・。
一体、〔臥龍〕だの〔伏龍〕だのと大天才視されていた
【諸葛亮孔明】は、何をしていたのだ!?
曹操軍の襲来を、しかも百万もの大軍団の襲来を予測していなかったと謂うのだろうか・・・・??
この直後、ただ慌てふためいて、ドタバタと遁走するしか無かった劉備ファミリーの動きを見れば・・・・その軍師であった諸葛亮の責任は重大である!
ーーズバリ言えば、
孔明、軍師失格!
・・・・その無為無策ぶりを批難されても、返す
言葉も見つからぬ”大失態”である!!
・・・・一体、何で、こんな事に成ってしまったのか??
その辺りの事情を審らかにする為に、我々は、この直前に該当する 〔空白の一年半〕 を検証してみる事としよう。
先ず、その手掛かりとして、『正史』に記述されている唯一の
部分を観てみよう。それは、『諸葛亮伝』と『先主伝』とに夫れ夫れ一ヶ所ずつ記されている箇所である。このうち、より重要なのは、言う迄も無く、『諸葛亮伝』の方である。
・・・・である筈なのに・・・・其処に記されている内容は、一読する限り、どこか”見当外れの出来事”に過ぎ無いのである。
(別の意味では”有名な出来事”では有るが)兎に角、観てみよう。
 ーー『正史・諸葛亮伝』--より
ーー『正史・諸葛亮伝』--より劉表長子琦亦深器亮。劉表の長子の琦も亦、深く亮を器とす。
表受後妻之言。愛少子琮不悦於琦。
表は後妻の言を受け、少子の琮を愛し、琦を悦ばず。
琦毎欲與亮謀自安之術。琦 毎に亮と自安の術を謀らんと欲す。
亮輒拒塞。未與處畫。亮 輒ち拒塞し、未まだ與に処画せず。
琦乃將亮游觀後園。共上高楼。飲宴之間令人去梯。因謂亮曰。
琦 乃ち亮を将に後園に游観し、共に高楼に上り、飲宴の間、人をして梯を去らしめ、因って亮に言いて曰く、
今日上不至天。下不至地。言出子口入於吾耳。可以言未。
「今日、上は天に至らず、下は地に至らず。言は子の口より出で吾が耳に入る。以って言うべきや未まだしや」と。 亮答曰。亮 答えて曰く、
君不見申生在内而危。重耳在外而安乎。
「君見ずや。申生は内に在りて危く、重耳は外に在りて安きを」と。
琦意感寤。陰規出計。會黄祖死得出。遂爲江夏太守。琦の意、感寤し、陰かに出る計を規る。たまたま黄祖死し、出づるを得、遂に江夏太守と為る。
その煽りを喰らって己の地位はおろか、下手をすれば命さえ危くなって来たのが、地元豪族の後ろ楯の無い『劉琦』であった。
既に成人していた劉琦は、以前から諸葛亮を高く買っていたのだが、事ここに及んで、己の生き残り策を孔明に相談したいと願った。然し、孔明の方は、その人脈から言っても「蔡一族」に近かった為、有力者達から無用な疑いを抱かれまいと、劉琦からの再三の招きにも応じず知らん顔し続けて居た。だが、いよいよ切羽詰まった劉琦は、或る宴会をとらえ、孔明と二人きりになる機会を強引に作った。劉琦とて孔明の立場は重々解って居たから、離れの高楼に昇った後、梯子を外させた完全な密室状態の中で、孔明から生き残りの為の最善の策を聴き出そうとしたのである。ここ迄されれば孔明も仕方なく、短時間で手短に、しかも遠廻しの故事に譬えて答えてやったのである。
(そんな密談の内容が、正確に後世に伝わる筈も無いのだが、
そこは古代の歴史家の腕の見せ所である。)
さて、その譬えに引用された『申生』と『重耳』の故事とはーー
春秋時代の晉の献公は、太子の「申生」が生まれた後に、異民族出身の後妻を迎えて子・奚斉をもうけた。だが、彼女の憎しみによって、都に居た「申生」は自殺に追い込まれた。その一方、異母兄の「重耳」の方は地方に逃れ、その後の諸国遍歴を経て、遂には故国に帰って【文公】と成った・・・・のである。
すなわち孔明は劉琦に対して、「重耳」の様に地方へ出て難を避け、後事に備えよ!・・・・と示唆したのである。そして、其の意を察した劉琦は、たまたま空きの出来た「江夏郡の太守」として、州都の襄陽を去り、差し迫った危機を回避し得たのであった。
・・・・と云う事になっているのだが・・・・
然し、この後の史実の結果から観ると・・・・寧ろ二人の密談を
仕掛けたのは諸葛亮の方ではなかったのか?・・・・と思われる
フシがある。
何故なら、劉琦を取り巻く状況は、誰に相談する必要も無い程に明々白々であった。既に、荊州の権力中枢はガッチリと固められており、劉琦自身には選択の余地など全く無かったし、彼が孤立無援である事も亦、動かし難い事実であった。つまり、諸葛亮から示唆を仰ぐ迄も無く、劉琦には”地方に難を避ける”方途しか無かったのである。もし、この2人に密談が持たれたとすれば、そのメリットは断然「江夏」に劉琦を送り出した諸葛亮の方にこそ求められるのである。
江夏郡には「夏口」と云う長江沿いの軍港が在り、其処は【呉】との国境城市でもあった。いずれ《呉国との同盟》を天下三分の要と考えている諸葛亮にとっては、この劉琦の水軍と兵力は呉国との交渉に臨む際の有力な切り札と成り得る。
劉琦が江夏太守として保有するであろう1万余の軍兵と、其の船艇群は、対等な立場で同盟を持ち掛けようとする時、無くてはならなぬ持ち駒となる・・・・密談を持ち掛けたのは、寧ろ諸葛亮の方だったとしてもおかしくはない。少なくとも、この後の史実は、結果的にはそう動いてゆくのである。--だとすれば・・・・諸葛亮は、〔空白の1年半〕に於いて、全くの無為無策であったとは言えなくなるのだが・・・・。
次に、”より重大な情報”を与えて呉れる『劉備伝』の方を観てみよう。
 ーー『先主(劉備)伝』より--
ーー『先主(劉備)伝』より--
十二年。曹公北征烏丸。(建安)12年。曹公(曹操)、北のかた烏丸を征す。
先主説表襲許。表不能用。先主、表(劉表)に説き、許を襲わしむ。
表、用いる能わず。
曹公南征表。 曹公、南のかた表を征す。
會表卒。 たまたま表、卒す。
子琮代立。 子・琮 代わり立つ。
遣使請降。 使を遣わして降を請う。
先主屯樊不知曹公卒至。至宛乃聞之。
先主は樊に屯して、曹公の卒かに至るを知らず。宛(南陽)に至りて乃めて之を聞く。
遂將其衆去過襄陽。遂に其の衆を将いて去って襄陽を過る。
この『諸葛亮伝』と『先主伝』とが述べる、(曹操襲来迄の期間に於ける)孔明・劉備の言動を総合して観た時・・・・其処には荊州に間借りする”劉備ファミリーの悲しい限界”、
すなわち”居候の悲哀”が見えて来るのである・・・・・。
 ーーこの207年(建安12年)と云う年は・・・・47歳の劉備個人にとっては、諸葛亮という「名軍師」を迎え、「直系男児」を得ると云う未来に夢のふくらむ嬉しい年となった。だが、現実の政治となると、事はそう上手くは進まなかった・・・・
ーーこの207年(建安12年)と云う年は・・・・47歳の劉備個人にとっては、諸葛亮という「名軍師」を迎え、「直系男児」を得ると云う未来に夢のふくらむ嬉しい年となった。だが、現実の政治となると、事はそう上手くは進まなかった・・・・
劉備の受け容れ主である、荊州の【劉表】は健康を益々悪化
させ、周囲の重臣達の関心は、もっぱら”劉表亡き後の後継者
問題”・・・・即ち、我が身の保身へと向いていたのである。だから1客将(居候)の述べる対外政策への進言など、聴く耳も持たず、只々、権力闘争に明け暮れて居るばかりであった。
そんな状況下、(劉備が諸葛亮を迎えたか迎えないかのばかりの頃)・・・・曹操と対抗せんとする勢力にとっては、宿敵を滅亡の淵へと突き落とす”大チャンス”が現出したのだった。すなわち・・・・・
ーーこの207年の春の終わり・・・・
天下を窺う【曹操】が動いたのである。
第1章で詳述した如く、《官渡決戦》の大勝利以後、宿敵の
「袁一族」を地の涯て(北辺の烏丸族領内)に追い込んだ曹操は、全国制覇の道筋として、今や百万を呼号し得る大軍団を、如何に動かそうかと、豪勢で贅沢な選択に迫られていたのであった。
ーー曹操にとっては・・・・
北(遼東)か?南(荊州)か?ザッツ・クエスチョン!
・・・・の問題であった。
重臣達の大方の意見は、『荊州への南征論』であった。
もはや取るにも足らぬ敗残者と成り果てた「袁尚」・「袁熙」の2名など、放って置いてもノープログレム、後廻しで充分であった。
それよりは、国力充実・全く無傷の〔荊州・劉表を片付ける〕のが最優先課題の本源的問題である!と観たのであった。
だが、曹操の決断は違った。衆目の一致する『荊州への南征論』を却下して、若き軍師・郭嘉の『北伐先攻論』を採用。
全軍体制で北上を開始したのである。
その目的地である遼東・《烏丸族》の領土は、片道だけでも1000キロの大遠征となる。 だから、どんなにスムーズに事が
運んだとしても、往還には半年以上は懸かる筈だ。それでも曹操は、敢えて北伐を優先して、全力を以って北上を開始したのだった。その様は丸で、百獣の王である巨獅子が、たった1匹の小鼠に全力を奮って立ち向かうこの如くであった。ーーだが然し・・・・その結果として、今や曹操の根拠地・中原一帯はガラ空き状態と成ったのである。多少の守備軍は残置していったとしても、高が知れていよう。
もし、荊州の全軍を挙げて攻め込めば、許都に居る「献帝」を奪う事はおろか、曹操一門の拠城である『業城』をも陥落させ、一気に曹操を根無し草の浮遊軍にしてしまう事も可能となる!今や覇業の最右翼に在る曹操を、その位置から引き摺り下ろし一発逆転する絶好にして唯一最大のチャンスが出現したのである!!
--だが・・・・そうした情勢の出現を”チャンス!”として捉える思考は、今の荊州内に於いては、劉備集団のみでしか無かったのである。死の床に伏す『劉表』には既に気力無く、それに代わる、事実上の実権者である『萠越・萠良』兄弟の持論は、【曹・魏】への臣従・帰属であった。これは、荊州内に住む諸豪族の大多数が支持する生き残り策だったのである。
そんな折に、いくら劉備が『曹操を倒す絶好のチャンスですぞ!』などと遠吠えしたとしても、馬の耳に念仏、蛙の面にションベンであった。否、それ処か、そうした劉備の動静は、彼ら恭順派にとっては、不必要な波風を立てる”厄介者”とさえ映る様に成ってゆく
・・・・そして遂には、”要注意人物・危険人物”と見做され、劉備ファミリーが気付かぬ裡に、その立場は荊州中枢部から隔絶・孤立化させられてゆくのである。即ち劉備陣営は、情報の提供が恣意的に遮断された、ツンボ桟敷に置かれる事を余儀無くされてゆくのであった。
《・・・・戦った処で、とても勝てる相手では無い。無用な抵抗をするより、いち早く曹操に協力して、事後の地位保全や栄達を確保して措くに限る・・・・》そんな彼等の自己保身の為の結束は固く、決して部外者の劉備に、必要最低限以上の軍兵を与えようとはしなかった。ナンバー3の『蔡琩』には、若干その気配も感じられるが、自分の娘ムコ(劉琮)を新君主に就かせる為には、萠兄弟を敵に廻す訳にはゆかない。ーー諸葛亮が劉備に出仕する以前に、着々と築いて措いた人脈のうち、最大の突破口であるべき「蔡琩」にしてからが、この有様であった。
--すなわち・・・・【曹操】と云う巨人が発する
圧倒的な衝撃波の前には、一書生が準備した
小賢しい措置など、何の役にも立たずケシ飛んでしまった・・・・と言う事である。
遙か2000キロの北方に居るにも関わらず、曹操のオーラは、現地に居る孔明のサロン人脈策など全く寄せ付けず、通用させぬ程に巨大であったのだ!!
《--嗚呼、やんぬる哉・・・・!》先々の苦労が思い遣られる。
《それにつけても・・・・》と、諸葛亮はつくづく思い知らされた。かく有るを見越して、果断に行動を起こした『曹操』と云う男の凄さ、その巨大さが、現実の兵力差と共に、改めてズシンと骨身に沁みる結果となったのである。
ーーかくて、荊州の207年(建安12年)は、空しく時間だけが過ぎ去る裡に暮れていった。・・・・そして、ついに・・・・
 運命の208年建安13年が巡って来た!
運命の208年建安13年が巡って来た!
この年の12月に、三国志世界を切り裂く大事件ーー
《赤壁の戦い》が勃発するのである。
そして、この世紀の大決戦には、
三国志の英雄達が総登場する
事となる。
だが今・・・・荊州の地は、見かけ上は常に変わる事も無く、穏やかな時の流れの中に在った。その1月~6月までの半年間は、是れと言った動きが全く感じられぬ儘に過ぎ去った。
ーー8月・・・・荊州の主・【劉表】が他界した。 僅か1代・10余年にして、荊州を天下随一の大州に育て上げた男の死であった。単騎赴任して来た時、彼の齢は既に50歳であった。その初老からの男は、荊州を〔天下必争の地〕と、誰もが認める程に豊饒の地として遺し去った。享年67歳。
天は、せめてもの報いとして、劉表を「荊州の主」で在るまま、
その一生を終わらせたのである。
『外貌 儒雅ナレドモ、心ハ疑忌多シ。』
『謀ヲ好メドモ決無ク、才有レドモ用ウル能ワズ。善ヲ聞ケドモ
容ルル能ワズ。』 『座談ノ客ノミ。』
『道相イ越バザルニ、臥シテ天運ヲ収メ、蹤ヲ三分ニ擬エント
欲ス。其レ猶オ木禺ノ人ニ於ケルガ如キ也。』
『嫡ヲ廃シテ庶ヲ立テ、礼ヲ捨テテ愛ヲ崇ブ。』
--と、史書には記されている。が、劉表の遺書に示された後継者は・・・・長男・『劉琦』であった筈である。
《己1代で築き上げたこの荊州の地を、むざむざと曹操の手に渡してなるものか!》の思いは、劉表の胸中に有ったと思われる。そして其の思いを実行して呉れる可能性が有るのは、年齢的にも、成人している「劉琦」でしか有り得ず、気概の面でも、父親の背中を見て育った長男でしか有り得無かった。
それに比べ、後妻・蔡夫人の産んだ「劉琮」は13歳に過ぎず、降伏派の飾り物である事は明白だった。然し、その遺言は当然の如く揉み消され、死後ただちに発表された世継ぎは「劉琮」であった。何の騒ぎの起こる事も無く、劉表の遺志は無視され、その座は決定した。長男「劉琦」の方は、事前に江夏の地へ太守と謂う名目で追い遣られており、お家騒動を起こす糸口さえ奪われていたのであった。降伏帰順派の首魁で実権者の『萠越』に、ぬかりは無かった。彼には既に曹操から熱烈なラブコールが掛かっていた。それ程の”逸材”である。諸葛亮の付け入る隙は皆無と言える程のガードの固さであった。

諸葛亮が三顧の礼で劉備に迎えられてから1年・・・・建安13年(208年)の今現在、劉備ファミリーの所在地は、荊州の州都・『襄陽』とは漢水ひとつ挟んだ、対岸の『樊城』であった。それ以前は、もっと北方の「新野」であったが曹操の来襲を危惧した劉表の措置によって、防衛線を州都寄りに退かせられたのであった。現代では、シャンファン市=襄樊市と云う一つの都市である事からも判るように、距離的には荊州の中枢に居拠してはいたのだが・・・・
劉備一行は未だ、曹操軍の動きを全く知らない。
それ処か、〔劉表の死亡〕や〔後継者の正式決定〕、更には〔降伏の決定〕と〔使者派遣の事実〕などなど、今後の方策にとっては必要不可欠な重大情報を、何ひとつ掴めて居無いのであった。 (※ 詳細は【第10章】にて描く。)
是れは、信じられぬ様な事実である!百万もの大軍が、眼と鼻の先に現われる迄、その動きも気配すら気付け無かったとは?
孔明でなくとも、時局の流れ・曹操の戦略・彼我の状況等々を勘案すれば、その情報収集には心血を注ぎそうなものである。何とも不可解で、手抜かりな話しである。とても信じられぬ。
それだけ曹操側の「機密保持」・「情報管理」・「状況秘匿」のガードが完璧であったと云う事になる。萠越・萠良・蔡琩らを含めた曹操側の、防諜体制の緻密さ・完璧さが際立つ。
とは謂え、こっちに其の気さえ有れば、80万の大軍が3ヶ月も前に動き出した事くらいは掴める筈である。つまり劉備一行、就中軍師として招かれた諸葛亮は、それを怠ったとしか言えない
天下三分の理想を大いに語り、大戦略を構想するのも結構だが直面する現実に対して、何らの手も打って居無かったとしたら、諸葛亮孔明は全くの未熟者、この時点に於いては、”軍師失格”としか謂えまい。迂闊と言うのも憚られる様な、この大失態を失態と呼ばずして何と呼ぶのか?曹操の緩急自在な戦略・用兵操作に完全に翻弄され、虚を衝かれてしまっている。ーーそれにしても、僅か50キロの鼻先に近づかれる迄、その大軍の動きを察知でき無かったとは、余りにも未熟で拙い。
全ての史書(書物)は、それを隠蔽秘匿し、むしろ情報提供をシャットアウトした「劉琮派」を悪罵して、諸葛亮には落度は無く、已むを得無かったとするのだが、それは諸葛亮に対する冒涜である。
何故なら、諸葛亮は、そのスタートの未熟さをキッチリと自覚し、その大失態をバネに、大軍師として未来に立ち向ってゆくのであるからに外ならない。我々は其の事実を受け容れてこそ、初めて真実の【諸葛亮孔明】に巡り会えるのだ・・・・。
時は西暦208年、建安13年である。
そして月は秋・9月・・・・・若き諸葛亮は、曹操軍80万の襲来の報に蒼ざめ、そして一瞬、立ち竦んで居た・・・・!!
さて、謂わずも哉であるがーー本書の《第1部》は・・・・
凄ご過ぎる男・【魏の曹操】、
颯爽たる男組の【呉の孫権】、
ケタ外れのダメ男・【蜀の劉備】の3大英雄が、
西暦208年の《赤壁の戦い》で会同する場面を
目指して、夫れ夫れに書き進められて来ている。
そして今ようやく、その3英雄の中で、『劉備陣営』が一番
乗りで、其の208年時点に到達した訳である。
ーー残るは、北方への大遠征を控える『魏・曹操陣営』と
兄であった「小覇王・孫策」を失って悲嘆に暮れる
『呉・孫権陣営』
・・・・その2つ勢力の208年への到達である。

--では、我々は再び時空を遡って、
『神か魔か人か!?』と畏怖される、
覇業に最も近い男・・・・・
【曹操孟徳】の元へと引き返し、彼が
百万の大軍を率いて、突如、208年の9月に
諸葛亮の前に現われて来る迄の道程を追い、
クライマックスの《赤壁の大決戦》に向かおう。
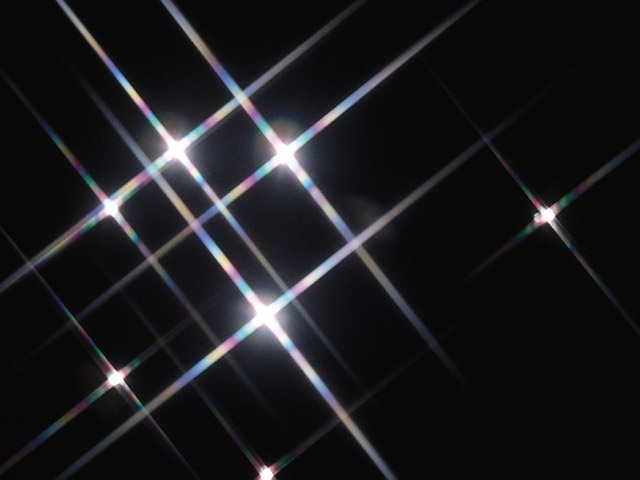
【第8章】 神か魔か人か (プロローグ) →へ