

江東の全土を平定、袁術からも独立を果し、まさに意気天を突く〔小覇王〕!ーーだが、そんな【孫策】にも・・・此の処時折、苛立ちの表情が垣間見られる。原因は、本人自身が1番よく分って居た。然し、それを人前に吐露できぬ処に、君主たらんとする「王者の孤独と焦燥」とが在った・・・・・
ーーそんな或る日、孫策は、呉郡の城門の楼(閣)の上で、部将や賓客達を集めて宴会を主催した。 やがて宴も半ばに達した頃、その門の下を小走りに通り過ぎる者が在った。その男は盛装し、仙人金華(かハ鋤ノ意)と呼ばれる、漆で絵が画かれた小さな函を地に引きずっている。たまたま窓際に居た部下の1人が其の物音を聞きつけて首を伸ばした。
「ーーあっ、于吉さまだ!」その者は思わず声を挙げた 「何、道士さまがお通りか!?」
 「おお、于吉さまじゃ!」窓際にドッと皆が群がったかと思うと、主君が主催する公式な会合であるにも関らず、何と部将や賓客の3分の2までが、我先にと楼を降りだしたのである。そして于吉を出迎えて礼拝し、会合などはそっち退けになってしまった。「皆さ〜ん、すぐに席にお戻り下されませ〜!宴会係の役人が声を枯らして呼び掛けるが、誰一人としてそれに応じようとする者が居無い。
「御前でありますぞ!失礼ではありませぬか!どうぞ、すぐお戻り下され〜〜!!」
「おお、于吉さまじゃ!」窓際にドッと皆が群がったかと思うと、主君が主催する公式な会合であるにも関らず、何と部将や賓客の3分の2までが、我先にと楼を降りだしたのである。そして于吉を出迎えて礼拝し、会合などはそっち退けになってしまった。「皆さ〜ん、すぐに席にお戻り下されませ〜!宴会係の役人が声を枯らして呼び掛けるが、誰一人としてそれに応じようとする者が居無い。
「御前でありますぞ!失礼ではありませぬか!どうぞ、すぐお戻り下され〜〜!!」
−−突然、火の消えた様になった宴会場に、独りポツ然と取り残された孫策・・・・初め、苦虫を噛み潰した如くであった顔が、次第に屈辱で真っ赤になっていく。
《おのれ、者ども!この孫策伯符を愚弄しおって!俺はお前達の主君なのだぞ!!》・・・・口に出して怒鳴りたい衝動を、やっと抑えているのが判る。僅かに居流れる者達との間にも、気不味い空気が生じてしまう。「ーーウグググ〜〜・・・・許せぬ!!直ちにきゃつを引っ捕えて地下牢に放り込めえ〜ィ!この儂を蔑ろにし政道を妨げる不届き者は生かしては措かんぞ!
その素っ首を斬り落とし市に晒してくれるわ!」
このところ、君主たらんとする己の地位の危弱性に苦悩していた孫策である。そのイライラが爆発した。但し、口惜しいかな、今の段階では、それを家臣団に強要できる状況ではなかった。年も若く、肩書きとて正式には、つい先頃うけた〔会稽郡太守・騎都尉〕でしかない。家臣団の誰しもが、孫策を軽く見る心算など毛頭ないし、「小覇王」とさえ言い合っているが、然し現実には未だ未だこの有様なのだ。主君とは思っても、絶対的君主だとは観られていない。ーーそれでは、これから先が思いやられる。今ここで断固とした専権を家臣達に示さねば、君主として立つ瀬が無い・・・・そこで、その怒りの鋒先は肝腎な家臣団へでは無く、偶々そこを通っただけの【于吉】の方に向けられてしまったのである。これはどうみても王者のヒステリーだ。だが、一旦口に出して命じてしまった以上、今更あとには退けない。そんな事をしたら、ますます、君主権の弱体化を招いてしまう。
「于吉は殺す!」・・・・と息巻く小覇王。ーー然し・・・・さあ、それからがまた大騒動であった。孫策が本気であると分かるや、于吉を信奉する者達は皆、その妻女達を孫策の母親(呉夫人)の元へ遣って、于吉の助命を請わせると云う行動に出たのである。その人数たるや、呉夫人の屋敷を十重二十重に押し包み、異様な熱気を醸し出した。もともと呉夫人自身からして、熱心な信奉者の一人であり、于吉とは古くからの顔なじみでもあった。そこで呉夫人は、直ちに我が子(孫策)の元へ訪れると、強い口調で諫言を呈した。
「于先生は軍の為にも幸運をもたらし、将士達の健康を守っております。殺してはなりません!
当時の人心の在り様としては、之が最も普遍的な常識と言えよう又、この母系性社会の名残りの強い呉会地域では、母親は一種女神として崇めの対象でもあり、その発言は他国以上に重いものであった。実際にこれ迄にも幾度となく、孫策は母(呉夫人)の言を受け容れて来ていた。・・・だが然し今回ばかりは孫策の意志は頑くなで女神たる母親の忠告をも撥ねつけた。
「あ奴は妖しげなデタラメを行ない、人々の心を巧みに幻惑し、ついには部将達に君臣の礼など顧慮する事もなくこの私を放ったらかしにして、皆、楼を降り、自分を礼拝させると云う様な事までさせました。これは由々しき問題であって、生かしておく訳にはゆかぬのです!」
これに対し呉夫人がどう反応したかは記されていないが賢夫人の誉れも高い彼女の事だから、君主権の確立と云う【最重要課題】を即座に理解したと思われる。と言うより、対外向けの母子によるパフォーマンスであったのかも知れない・・・・いずれにせよ、頼みの綱の母親もダメだったと知れるや、信奉者達はいよいよ
挙って直接行動に出て来た。配下の部将達は連名で請願書を奉り、その中で事情を説明し、于吉を赦して欲しいと公式な形をとったのである。これはもう、主君と家臣達とを巻き込んだ、れっきとした”事件”である!
 処で、人々をそう迄させる、この【于吉】とは一体何者なのか!?
処で、人々をそう迄させる、この【于吉】とは一体何者なのか!?

平たく言えば〔仙人〕、詰り《道教》の伝道士・道士サマとして、人々から崇められている男であった。それも開祖(に近い)的な存在として、単なる道士ではなく、”仙人サマ”として尊崇されていた。−−その最も有名な事蹟?としては・・・・
道教の最も古い教典とされる『太平青領書』を世に残したとされる事である・・・5代前の順帝の御世、『宮崇きゅうすう』なる者が宮廷に参内し神書を帝に献上した。それは白い絹に朱の罫(けい)を引いた書物で、太平青領道(太平青領書)と名付けられ、全部で百余(170)巻あった。これがのち、あの黄巾党の主催者となった「張角」などに引き継がれ、現在も巴蜀で栄んな太平経
(五斗米道)へと脈絡している。ーーちなみに其の『太平青領書』
実は『宮崇』の師である【于吉】が曲陽の水辺で手に入れた物であり、それを弟子に持たせて献上させたのだと言うーーという事は、現在の于吉の年齢は既に100歳近いと云う事になる。
 【于吉】は除州北方の瑯邪の出身で、先祖以来、東海地域(東方)に寓居し、呉郡や会稽一帯(呉会)を行き来して、精舎(教会・寺院)を建て、香を焚き、道教経典を誦読し、符や神聖な水を用いて病気の治療を行っており、呉会の人々には于吉を信仰する者が、甚だ多かったのである。但し彼には太平道(黄巾党)の【張角】や、今も隆盛を極めている五斗米道(巴蜀地方)の【張魯】の如き、政治的野心は全く無い。ひたすら純粋に宗教の布教と救民活動とに専念している個人であった。蓋し、とんだトバッチリを受けてしまった訳であるーーだが、君主はニベもない。
【于吉】は除州北方の瑯邪の出身で、先祖以来、東海地域(東方)に寓居し、呉郡や会稽一帯(呉会)を行き来して、精舎(教会・寺院)を建て、香を焚き、道教経典を誦読し、符や神聖な水を用いて病気の治療を行っており、呉会の人々には于吉を信仰する者が、甚だ多かったのである。但し彼には太平道(黄巾党)の【張角】や、今も隆盛を極めている五斗米道(巴蜀地方)の【張魯】の如き、政治的野心は全く無い。ひたすら純粋に宗教の布教と救民活動とに専念している個人であった。蓋し、とんだトバッチリを受けてしまった訳であるーーだが、君主はニベもない。
「昔、南陽の「張津」が交州刺史であった時、いつも赤い頭巾を被り、琴を鳴らし香を焚いて、庸俗な内容の道書を読み、政治教化の助けとなすのだと言っていたが、結局は南方の異族に殺されてしまったではないか!(史実では張津は未だ生きており、孫策がこんな事を口走るのは不可能なのだが) こうした事は全く益も無い事であるのに、諸君は未だそれが分っておらぬのだ。こいつはもう亡者の帳簿に其の名が載せられている。上書などして(貴重な)紙や筆の無駄使いなどせぬようにせよ!」
役人をせかせて于吉を斬らせ、その首を市場に晒した。尚、当時は、高齢者と幼児には刑を加えぬ・・・・のが「礼」の定めであり、特に100歳を超える人間が自領に居れば、皇帝みずから会いに出向き、敬意を表して慈しむのが〔聖王政治の極致〕とされ
”君主の誉れ”となった。にも拘らず孫策は于吉を殺してしまった
−−・・・以上は『江表伝』なる2・5流史料(裴松之の補註)による話しである。御多聞にもれず此の書は寧ろ事後の「道教の神秘」を強調するが如く、こう締め括っている。
『然し于吉を信仰する者達は、彼が死んだとは考えずに、死んだと見せかけて仙去(せんきょ)・尸解(しかい)したのだと言い于吉を祭って福を求める事を止めなかった』・・・・・と。
 ちなみに《尸解》とは、仙人に成るに際し、竹杖などを身替りにして、外見的には死んだと見せかけて仙去する事とされていた。面白いのは、仙人になる成り方にも上・中・下のランク付けがなされている点だ。
ちなみに《尸解》とは、仙人に成るに際し、竹杖などを身替りにして、外見的には死んだと見せかけて仙去する事とされていた。面白いのは、仙人になる成り方にも上・中・下のランク付けがなされている点だ。『抱朴子』・論仙篇(こうした類の書が真剣に著されていた)に曰く、
上士は、形を挙げて虚に昇る・・・これを【天仙】と謂う(白日昇天) 中士は、名山に遊ぶ。・・・・これを【地仙】と謂う。
下士は、先に死し後に蛻する。(遺体をのこして去る)これを【尸解仙】と謂う
(これだと于吉は、仙人として未だ未だ未熟者だった?)
 処で、『正史』には于吉と云う存在は、その名前すら1ヶ所も出て来ていない。陳寿はわざわざ「魏書」に〔方技伝〕という種々の特技者を伝えるコーナーまで揃えているが、そこにすら登場していないのである。于吉なる人物が魏国と無関係な土地に居た為とも考えられる。いずれにせよ、その実在自体が怪しまれる人物である。つまり、孫策による〔于吉殺し〕なる事件の有無は根拠に乏しいものなのである。ーーではあるが、筆者は敢えて、ここでこれを紹介する。何故なら、事のいきさつはどうであれ、また正史に記述は見えないが・・・どうも、この孫策による于吉殺しは有ったように思わされてしまうからだ。(補註を記した【裴松之】の
処で、『正史』には于吉と云う存在は、その名前すら1ヶ所も出て来ていない。陳寿はわざわざ「魏書」に〔方技伝〕という種々の特技者を伝えるコーナーまで揃えているが、そこにすら登場していないのである。于吉なる人物が魏国と無関係な土地に居た為とも考えられる。いずれにせよ、その実在自体が怪しまれる人物である。つまり、孫策による〔于吉殺し〕なる事件の有無は根拠に乏しいものなのである。ーーではあるが、筆者は敢えて、ここでこれを紹介する。何故なら、事のいきさつはどうであれ、また正史に記述は見えないが・・・どうも、この孫策による于吉殺しは有ったように思わされてしまうからだ。(補註を記した【裴松之】の"功罪あい半ばする処"でもあるが)次に紹介するのも亦、裴松之の補註に載る、2つ目の〔于吉殺し〕の話しである。然も今度は、『捜神記』 と云う、そのタイトルからして、それこそ 非科学的な、《超常現象集》であり、3流以下の与汰史料である事間違いなしと妙な折紙が付いた代物である。ーーが然し、史実として観るのではなく、当時の人々が少なからず抱いていたであろう”ある種の時代的雰囲気”を識る上では、あながち無駄ではあるまいと勝手に判断して筆を進めてゆく事とする。作者は『晋書』を著した干宝である。
『孫策は、長江を渡って「許都」を襲撃しようとし、于吉を連れて軍を進めた。折りしも
ひどい旱に遭い、どこもかしこも乾ききっていた。孫策は船を引いて速やかに進むよう将士達を督励し、時には朝早くから陣頭に立って叱咤していた。にも拘らず見てみると部将や軍官達の多くが、于吉の元に集まっていた。孫策はこれに激怒した。
「儂が于吉に及ばぬと云うので、先ず彼の元に集まって、彼の言いつけを勤めて実行しておるのか!」 すぐさま于吉を捕えさせ、前に引き出して詰問。
「旱続きで雨が無く、行軍は難渋し、前進に時間ばかりかかる。だからこそ儂は、早朝から陣頭に立っておるのだ。然るにお前は、俺の心配事など顧慮せず、船中に安閉と座って妖しげな態をなし、儂の部下達を駄目にしてしまっている。お前をこのまま生かしておく訳にはゆかぬ!」
于吉を縛って地面に転がし炎天に晒して雨を請わせた。
「もしお前が天を感ぜしめ、日中に雨を降らせる事が出来たなら赦してやろう。さもなくば誅殺する!」・・・・・と、俄かに雲気が立ち昇り、空は真っ黒になって、日中になる頃、どしゃぶりの雨がやって来て、谷川には水が溢れた。将士達は喜び、于吉はきっと赦されるだろうと思い、みな彼の元に慶賀と慰いの為に集まった。処が、孫策は于吉を殺してしまった。
「これは、たまたま自然現象が今起きただけの事だ!奴の妖術の為ではないのだ!」
将士達は悲しみ、皆んなして、その死体を人目につかぬ場所に安置した。 夜になると突然に再び雲が起こって、死体の上を覆い、次の日の朝に行ってみると、死体はゆくえ知れずになっていた−−。』
(これだと、于吉の仙人ランクは、少し上がっている?)・・・・要は3級とは言え、これら複数の史料に、「于吉は孫策に殺された」と云う事になっている点である。全くのデタラメとは即断し難い所以ではある。
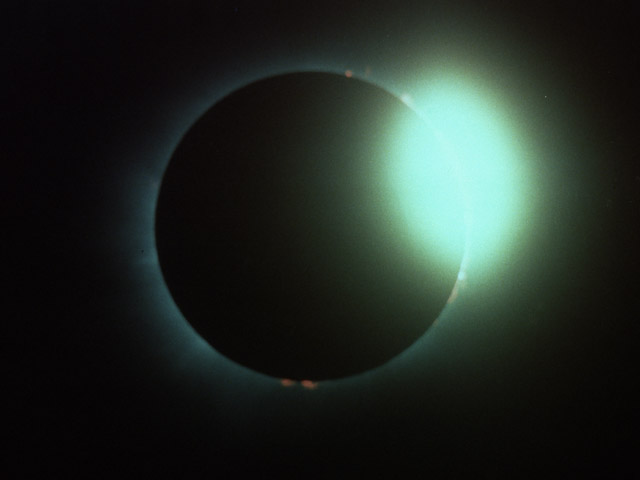 《面白くないな・・・・》一見した限りでは全てが順風満帆で何ら非の打ち処も無いように見える。現に孫策自身、今も快活に、誰とでも明るく接しては、笑い声が絶える事はなかった。それが彼の大きな魅力の1つでもあるし、孫策とてそれが少しも苦にはならない。だがその一方、小覇王の笑顔の下には、抑え難い不満が鬱積してきているのも亦事実であった。
《面白くないな・・・・》一見した限りでは全てが順風満帆で何ら非の打ち処も無いように見える。現に孫策自身、今も快活に、誰とでも明るく接しては、笑い声が絶える事はなかった。それが彼の大きな魅力の1つでもあるし、孫策とてそれが少しも苦にはならない。だがその一方、小覇王の笑顔の下には、抑え難い不満が鬱積してきているのも亦事実であった。はっきり言えば・・・急激に膨張したこの大軍の中で、忠誠心のみで純粋に己に付き従う者の数は、ほんの一握りでしかないと思われる。冷静に観て、孫策の名の下で、ひと旗あげてやろうとする者達の《連合体》と言ってもよいかも知れないーーこれは創業者たる者の定めであり古今東西共通の君主の悩みと言えよう。新しく興った勢力には、人心を引きつける魅力がある一面、その配下に加わった者達にしてみれば、歴代に渡って厚い恩顧を蒙ってきている訳でもない。謂わば、新たな契約関係を結んだばかりなのであった。そこには自ずと、新しい主の絶対性を省みない風潮が色濃く醸し出されてしまう。・・・・と言う事は、孫策の態度として、配下の者達への遠慮や阿諛も要求され、君主と言うより盟主・友人・客をもてなす主人として、常に一歩遜った言動を採り続けなくてはならぬ事を意味する。
だが、いかにその資質が英邁であるとは謂え、人間として練り上がるには21歳は未だ余りにも若かった。ともすれば、自分が絶対的君主として、何の制約も受ける事無く思いのままに振舞いたいと欲望するのは、その若さからみても当然の衝動かも知れないそれをグッと抑え込んで、己の腹の中に溜めていく・・・・誇り高く自意識の強い青年には、気骨の折れる日々でもあった。漢の高祖(劉邦)も後漢の光武帝も、創業時の鬱屈を、のちに、しみじみと述懐しているのであるから・・・・。
「狩りに行って参る!」クサクサした時の、孫策の唯一のリフレッシュ法であった。広い野原の中で唯独り、何事も忘れて夢中になって獲物を追う・・・・そんな時間を過してまた気を引き締め直して事に当たる。側近の重臣達に諌められようとも、これだけは止める訳にはいかなかった。その狩りの頻度が此処のところ増している孫策であった。江東平定戦が一段落した事もあるが、
”王者の鬱屈”も亦、日増しに募っていたと言えようか。そんな君主としての苛立ちを示すが如き事件が、『呉録』と云う(3級)史料に記されている。
 −−それは・・・・若き地元名士の殺害である。
−−それは・・・・若き地元名士の殺害である。殺されたのは【高岱】と云う人物だとされる。高岱の字は孔文と言い、呉郡の出身であった。生まれつき聡明で物事に通じ、金銭を惜しまず信義を重んずると云う、人望厚き人物であった。高岱の無名時代に、彼と交友を結んだ者達8人全てが、今は世に出て英俊と評されていた。 呉郡太守だった盛憲は、そんな高岱に白羽の矢を立て、上計(会計報告の為に都へのぼる)の役を任せ、孝廉に推挙した。そんな高岱の名を一踊世に知らしめる事件が20歳代半ばの頃に起きている。
《孫策は項羽に似ているから気をつけられたし!》と漢室に上表し孫策の怒りを買って、つい先ごろ謀殺されたあの【許貢】が存命中の出来事である。−−許貢がやって来て郡を乗っ取ると、高岱は(主君の)盛憲を許昭(月旦評の許劭とは別人)の家に案内して難を避けさせ、自分は陶謙(徐州牧)の元に赴いて、救援を求めた。然し陶謙がすぐには救援に応じなかった為、高岱は憔悴し血の涙を流して、湯水も喉を通らなかった。陶謙は、彼の忠義一途な気持が、申包胥(春秋時代末、呉が楚に進攻した時、楚の申包胥は秦に駆けつけて救援を求め、立ったまま食事もせず、昼夜を分かたず号泣して秦王の心を動かし、秦の助けを借りて呉の進攻を撃退した。)にも通じるのに感動して、軍を送る約束をし、許貢にも説得の手紙を書いた。高岱が陶謙の手紙を持って帰ってみると許貢は、卑劣にも彼の母親を捕まえていた。呉郡の人々は誰もが高岱のことを危ぶみ、許貢はかねてより彼に遺恨を懐いているから、行けば必ず殺されるであろうと言って、行くのを押し止めようとした。だが高岱は言った。
「主君に仕えては、己の身の危険など省みずに、主君の為に尽さねばならない。それに母が牢獄の中にあって、きっと来てくれるであろうと待っている。行って許貢に面会が出来たなら、事は自然と解決するのだ。」
そう言うと手紙を差し出し、みずから名乗り出た。許貢はすぐに彼を引見した。高岱は、気の効いた無駄の無い言葉で、巧みに自分のとった行動を説明した。その結果、許貢は直ちに彼の母親を釈放した。だが間もなく、許貢は帰してしまった事を悔やんで、高岱を追わせた。そして追手達には、「もし船に乗っている間に追いついたら江上で殺してしまうように!又もし既に江を渡ってしまっていたなら、そのまま見逃すように!」と命じたのである。然し高岱は、許貢が一旦は無事に帰らせても、きっと後悔をして、必ずあとを追わせるに違いないと、予め手を打っておいたのだった友人の張允と沈目昏に頼んで逃走用の船を用意しておいて貰ってあったのだ。だから許貢の元を退出するや否や、すぐさま母親を船に乗せて渡江しきり、道を変えて遁走した。追手達は高岱とは別の道を取った為、母と子は無事危難を免れることに成功したのである。この出来事があって以来高岱は故郷を捨て会稽郡の「余姚」で隠遁生活を送っていた。それが今、孫策の耳に達したのである。「是非にも欲しい人材じゃな!」孫策は直ちに彼に出仕するように命じ、会稽の丞の「陸昭」を使者として迎えにゆかせると、自分は礼を低くして接待しようと準備をするのだった。
聞けば高岱は、特に『春秋左氏伝』に深く通暁しているというので孫策は自分もそれを精読して、彼と一緒に議論してみたいと会う時を楽しみに待ちわびているのだった。・・・・・処が『呉録』では、ここに突然、「或る不可解な人物」が登場して来て、この両者に、悪魔の囁きを吹き込むのである。(直接、孫策と賓客=高岱とに話せる人物など極く限られた一部の側近でしか在り得ないのだが、呉録はそんな事には無頓着で、ただ”或る者”だけでお茶を濁して平気でいる。まあ、その程度の信憑性だと思って戴きたい。)
★『孫策に言う者(誰なのか不詳・不明)があった。・・・・
「高岱は、将軍さまが武勇一点ばりで、学問の才は無いと考え、心中密かに軽んじております。もし左伝を論じて、彼が分らないとお答えする事がございましたら、私の申し上げますように、彼は一緒に議論するに足らぬと、あなた様を軽んじている証拠でございます。」
一方、その者は、高岱に対しては次のように言った。・・・・
「孫将軍の御性格は、人が自分より勝る事を好まれません。もしお尋ねがあった時には、いつも分りませんと答えられれば、お気に召します。もし、いちいち議論だてをされれば、きっと危ない目に遭いましょう。」
高岱はこの言葉をもっともだと考え、孫策が『左伝』の議論を持ち出した時、「ときどきは分りません」と答えた。果せるかな孫策は腹を立て、自分を軽んじているのだと考え、彼を獄につないだ。
ーー・・・・埒も無い”与太話”である。だが、事の仔細は別として、どうも高岱殺害は史実であるらしい?・・・・だとすれば、注目すべきは、殺害にまで至ってしまった直接の理由である。『呉録』は、それをこう記している。
『高岱が獄に繋がれたと聞くや、知人交友のほか一般の人々までが、みな露天に座って高岱の釈放を請願した。孫策が楼に登って眺めると、そうした人々が数里の間を埋ずめ尽して居た。孫策ハ、高岱ガ人心ヲ得テ居ル事ヲ心ヨカラズ思イ、彼ヲ殺シテシマッタ。』・・・・この時、高岱の齢は30余歳であったという。本来であれば、孫呉政権の若きブレーンとして、永く君主を補佐したであろう逸材であった。初めは孫策もその心算で、丁重に迎えていたのに、君子豹変してしまっている・・・・筆者の意図は、もうお分かりであろう。
この【于吉】と【高岱】の両者とも、殺された当人には、何らの罪・咎も無く、寧ろ人望厚く、普段の孫策であれば、もろ手を挙げて大歓迎したであろう人材である。暗殺に脅え、己の命に服さなかった名医・【華陀】を殺害してしまった「曹操のケース」とも訳が違う。 ーー孫策の場合は・・・己を、〔君主として絶対視しない家臣団〕に対する鬱屈が、歪んだ形で噴き出した事になる。于吉・高岱の2人とも明らかに、そのトバッチリを受けた格好だ−−即ち・・・・〔君主権の不確定さ〕が昂じた、悲劇のシュチュエーションと取れるのである。
豪放磊落で、英俊闊達な『小覇王』と雖もその内面には創業者としての鬱屈した【王者の暗黒】が、澱の如くに潜んで居たのである・・・とは言え、この2つの事件とも『正史』には記述が無い両者とも名前すら出て来ない。他の2・3級史料から採ったものである。だから、我々の態度としては、孫策を矮小化する為にでは無く、創業主たる彼には当時、こうした一面も在ったであろうと、推察して措く事にして置こうではないか・・・・。
 更にもう1つ、我々としては気掛かりな点を、この若き王者の裡に見い出さざるを得無い。−−それは・・・・孫策の場合、他の群雄に比して、どうも”人の殺し方”についての”配慮”が足らぬ点である。無論、戦乱の世であれば、より多くの敵対者を亡ぼし、禍根を絶とうとして"三族皆殺し"も有り得た時代だ。そうでなくては生き残れない・・・だが然し、殺された者達にも遺族や遺臣は居るのだ。戦場での討ち死になら未だしも1対1・個人的に相手を抹殺してしまえば、恨みは更につのる。【許貢】や「厳與」は正に其のケースで、会見の席で自分の手によって、相手を謀殺してしまっている・・・・にも拘らず、曹操が暗殺者の影に脅えて寝汗をかく様な”小心さ”が見えない。 彼の若さと勇敢さとが、却ってアダになっている様に思われてならないのである。孫策自身が全く其の点を意に介さず、ひたすら前だけを見て邁進してゆく姿には、溌剌とした屑い青年の息吹を感ずると同時に、どこかしら一抹の不安を抱かざるを得無いのである・・・・・・
更にもう1つ、我々としては気掛かりな点を、この若き王者の裡に見い出さざるを得無い。−−それは・・・・孫策の場合、他の群雄に比して、どうも”人の殺し方”についての”配慮”が足らぬ点である。無論、戦乱の世であれば、より多くの敵対者を亡ぼし、禍根を絶とうとして"三族皆殺し"も有り得た時代だ。そうでなくては生き残れない・・・だが然し、殺された者達にも遺族や遺臣は居るのだ。戦場での討ち死になら未だしも1対1・個人的に相手を抹殺してしまえば、恨みは更につのる。【許貢】や「厳與」は正に其のケースで、会見の席で自分の手によって、相手を謀殺してしまっている・・・・にも拘らず、曹操が暗殺者の影に脅えて寝汗をかく様な”小心さ”が見えない。 彼の若さと勇敢さとが、却ってアダになっている様に思われてならないのである。孫策自身が全く其の点を意に介さず、ひたすら前だけを見て邁進してゆく姿には、溌剌とした屑い青年の息吹を感ずると同時に、どこかしら一抹の不安を抱かざるを得無いのである・・・・・・
だが彼は未だ、妻とて娶って居無い若者である。先走った心配よりも、我々は次に、彼と彼の親友である周瑜との、
”夢の様な結婚話し”を見てみよう。
人々から「孫郎」・「周郎」の美称で呼ばれている美男子が、2人揃って同時に、【大喬】・【小喬】と呼ばれる絶世の美女取りに挑むのだ。この〔美女姉妹の噂〕は、やがて遠く遥かな黄河の彼方まで轟き、業卩城に在る、美形好み・漁色家・「曹操」の耳に迄も達する程であった。
−−所謂・・・・・
《2郎、2喬を娶る!》 の段である。

【第86節】 美女姉妹分け娶り作戦 →へ